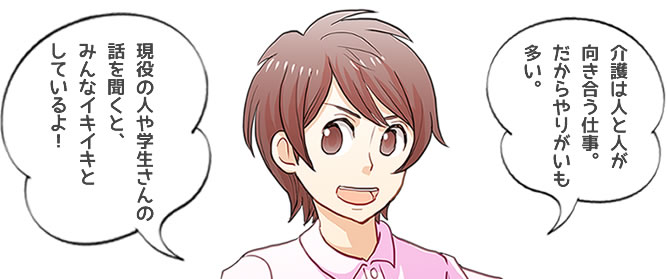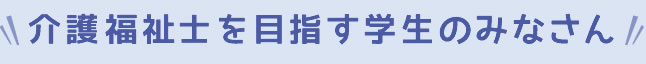取材:2017年1月6日
介護福祉士を志したのは、小学生のとき施設で暮らしていた祖父の面会に行き、介護福祉士の仕事を知ったことがはじまりです。そのときは介護福祉士になりたいと思いませんでしたが、中学校の職業体験でも施設に行き楽しかったことと、元々人の役に立つ仕事に就きたいという思いがあり介護福祉士を目指すようになりました。高校卒業後、すぐに現場実践を通して介護福祉士を目指すことも考えたのですが、大学で介護について深く学んでから就職することにし、現在学んでいるところです。
介護の道に進みたいと両親に話したときも、自分がやりたいならやりなさいという反応でした。私は小柄ですし運動部でもなかったため体力が無いので、そういう部分で苦労はするかもしれないけれど、と言われましたが反対はありませんでした。将来、介護が必要になったらよろしくね、とお願いされたくらいです。
話し好きなので実習ではコミュニケーションを取ることに苦労は感じませんでしたが、大学で介護技術について基本的なことを学んでいても、利用者さんの状況に合わせてどういう援助をするのか応用を利かせなければならない点が難しかったです。最後の実習は5週間あり、初めの頃は利用者さんから「この人、誰?」と言われるなど距離感がありましたが、途中からはいろいろお願いされたり、お礼を言われたりするようになり、うれしかったです。

受け持ちの利用者さんを決めてケアプランを立てる課題があり、病気で目が不自由な女性の利用者さんを担当させてもらったのですが、軽度の認知症もあり、最初のうち名前も覚えてもらえない状態でした。日が経つにつれ、声や手の感触で名前を呼んでくれるようになりすごく感激しました。顔は見えなくても声や体温、感触で覚えてもらえるのだということはとても印象に残りました。
将来は利用者さんや利用者さんのご家族に信頼され、悩みも話せると思ってもらえるような介護福祉士になりたいです。そのためにはコミュニケーションが大事です。私は利用者さんの一番近くで支援できる介護職として、ずっと現場で働きたいと思っています。
私は介護福祉士を目指すことにあまり悩みませんでした。大学には介護福祉士の資格が取りたくて入学したものの社会福祉士にも興味が出てきたという友人もいて、将来に関して迷っている学生がわりと多いです。ですから悩んでいる高校生の方には絶対にこの道に進むと決めなくても、とりあえずやってみるのもいいのではないかと思います。

私の通っている大学ではすべての介護実習を終えた後に「介護観」をまとめます。私は実習を通し、利用者さんが言っていることだけを支援しているだけでは、その人にとって本当に必要な支援はできないことを学びました。利用者さんの本心を汲み取り、支援として形にしていくことが「介護観」であるとまとめました。2回目の実習で介護老人保健施設に行った際、杖をついている利用者さんが、歩くとまた転んで車椅子になってしまうからあまり歩きたくないとおっしゃっていました。退所後、その方に偶然町で会ったら、一生懸命歩いていらっしゃったんです。「施設にいるときは歩くのが怖いとおっしゃっていたけど、今は歩いていらっしゃるんですね」と尋ねたら、「家族に迷惑を掛けないよう積極的に歩いている」とおっしゃっていました。その時、言葉にされないご本人の気持ちを汲み取ることが介護職にとって大事なことだと思いました。
4年次の卒業研究では、高校生が介護に対してどのようなイメージを抱いているのかをリサーチし、実際の介護の現場を知った後、そのイメージがどう変化するかを調べてみるつもりです。介護をめぐる現状を知ってもらい、介護福祉士に興味を持ってもらいたいと思います。