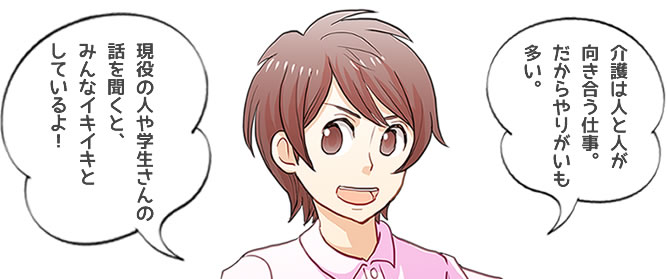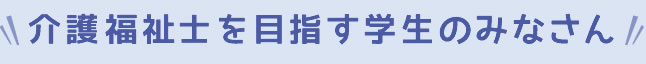取材:2024年11月5日
元々、同居していた叔父が脳梗塞による麻痺があり認知症を患っていたため母と祖母が介護をしていて、子どものころから介護が身近にある環境でした。何よりお年寄りが好きでしたし、大学の就職活動を始めるタイミングで、知らないお爺ちゃんが運転する自転車の後ろにお婆ちゃんがちょこんと座ってお爺ちゃんにつかまる姿を見て、すごくほっこりした気持ちになったこともあって介護の仕事に就きました。大学の学部は経営学部で、それまで福祉や介護のことを勉強したこともなかったのですが、若さゆえなのか「なんとかなるだろう」と思いながら、途中1年だけ他の職に就いた以外はずっと介護の現場に携わってきました。

一度、辞めてまた戻ってきた理由は、やはり利用者さんと関わることが好きなことに気付いたからです。利用者さんから笑顔を引き出せたときの喜びもそうですし、職場の仲間たちとの連帯感、チームワークを感じられるところも大きかった。落ち込んでいるときに支えてくれたり、元気になれるきっかけをくれる仲間がいる。いろいろな人と関わりながらチームプレーで仕事をしていけるところが介護職の魅力なのかなと思います。今、振り返ってみると一度、他の仕事を経験して外から介護職について考えることができたことで、前向きな気持で再度、介護職に取り組むことができたような気がします。
「あいち介護技術コンテスト2023」に出場したきっかけは上司の勧めです。人前で何かをやることに苦手意識があったので戸惑いながらも、やはりそこは克服していかなければならないとの思いもあり、自分のキャリアのためにも腹をくくって出場することにしました。
コンテストの出場は、介護技術や自分の体の位置など知識を更新する機会になりました。これだけキャリアを積んでいても、つまるところ声掛けが大事だということに気付けたのもコンテスト参加が大きかったですし、それは今、他の職員さんたちにも伝えている最中です。例えば一つのケアに対して「これからこうします」「こうしていいですか」と声掛けすることは、長く勤めていると、おろそかになってしまっている部分でもあったと気付きました。本人の答えを待ちながらケアをするのは時間もかかります。しかしそういうコミュニケーションが大事であり、利用者さんに安心していただけることだと実際の現場でも感じました。

出場に際してもロールプレイングみたいに上司や同僚に手伝ってもらい、人に見られながらやる環境と課題を作って、トレーニングを行いました。課題は直前まで何が出るかわかりませんので、それまでのキャリアで分からないことが出たらもう諦めようと。そんな思いでのぞみ、準グランプリを受賞した瞬間は実感が無かったのですが、その後「次は僕が出たい」と言ってくれる後輩が出たり、「こういうとき、どう介助すればいいか教えてください」って後輩が聞きにきてくれたりするので、参加して良かったなと思います。
僕はこの施設が好きで長く働いて、いろいろ経験させてもらっているので、今後は法人をより良くしていきたい。利用者さんに質の高いケアを提供していきたいですし、職員の働く環境をもっともっとよくして離職率を減らし、定着率を上げていきたいと思っています。
介護職は人の人生の最期に寄り添える、他には無い職業です。そして、利用者さんがどんな最期を迎えるかは介護職員によって大きく左右されるように感じます。最期のとき、ここで良かったと思ってもらえるか否かは介護職員次第。そんな職業ってなかなかありませんよね。例えば、何もしなくても時間は流れていくでしょうが、利用者さんが何か食べたい、何かやりたいと思ったとき、対応できるのは近くにいる介護職員です。利用者さんの望みに応えられたときは、他に代えられない達成感を感じます。やってあげられて良かった、希望をかなえることができて良かったと思えることが介護職の魅力ですし、大きなやりがいだと思っています。

僕は、介護職員になって初めて担当した利用者さんのことが今でも忘れられません。その方は母親と同じ名前で、お孫さんが僕と同じ年。すごく親近感を感じて、いろいろ良くしていただきました。その方の容態が夜中に急変して、僕は一生懸命胸骨圧迫をしていたのですが、みるみるうちに体が冷たくなって。だめかもしれないと頭によぎりながらも続けていたら、その方が「ありがとうね」って。そのときのことは今でも鮮明に覚えています。その方は最期のときに僕を選んでくれたのかなって、何かあるごとに思い出しますし、今まで続けてこられたのもこの経験があったからだと思っています。