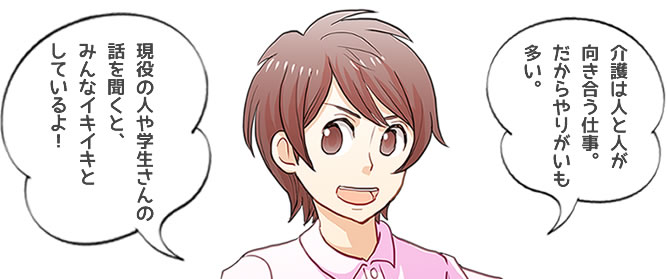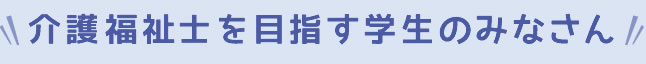取材:2019年10月30日
私は中学生のとき、自分に自信が持てるようになりたくて、高校は資格を取ることができる学校に進もうと考えていました。そして福祉科のある高校に進学し、学んでいくうちに、介護福祉への興味が徐々に増していきました。中でも福祉住環境コーディネーター(※)の勉強は、身体介護だけではない、福祉の幅広さを知ることができましたし、それまで少し敷居が高いと感じていた介護福祉がグッと身近になりました。
将来の仕事として介護職を意識し始めたのも高校時代です。要介護状態になった祖母の施設への入所がきっかけで施設職員の温かさに触れて、自分もこういうところで働いてみたいと考えるようになりました。
今の学校では、より深く介護福祉を学びたいという気持ちでいますが、介護の「知識」や「技術」が身に付くだけではなく、実習などで感じた「どうしてこの人には、こういうケアが必要なのだろう?」という疑問を解決するための「介護の根拠」を知る勉強もでき、そうしたことを学ぶ必要性もひしひしと感じています。
実は、両親は私が介護の道へ進むことに、初めは反対していました。しかし、一昔前とは違い、介護を取り巻く労働環境も良くなり、長く続けられる仕事だと理解してくれた今では、むしろ応援してくれています。学校で取得した介護関連資格の証書を見せたときはとても喜んでくれて、頑張っていることを認めてくれたようで私自身もうれしかったです。

カルテなどから知った生活歴によれば、一緒に暮らしていた奥さまが高齢になり、介護が続けられず入所に至ったとのこと。「お前」とは奥さまのことで、私のことを奥さまだと思われたようなのです。たとえ勘違いであっても、その一言は利用者さんに寄り添うことができた結果か、ご本人にまるで家にいるような安らぎを感じていただくことができたため、言葉にしていただけたのではないかと思えて、介護のやりがいに触れた瞬間でした。
卒業して介護職として働くようになっても、笑顔を絶やさず、誇りをもって仕事がしたいです。施設を自分の家だと思っていただけるよう、私が入居者さんの疑似家族となり、日々の小さな変化にも気付けるような介護職員を目指します。
学校での講義や実技、実習先での経験を通じて気付いたことがあります。それは、介護福祉に興味を持つこと自体がすばらしいということ。たまたま私の場合はそれが10代の半ばでしたが、早すぎることも遅すぎることもないと思っています。現に社会人の方も一緒に学んでおり、色々な面で刺激をしあって、共にとても有意義な学生生活を送っています。

卒業後、私は介護施設へ就職し、人と関わる仕事をすることになるので、日常から相手の気持ちを理解しようと心掛けています。例えば相手が怒っていたとしても、そこには理由があるはずです。「どうして怒っているのだろう」と思いを巡らせて、深いコミュニケーションをとろうと努めることで相手を知る。端的に言えば思いやりを持つということですが、介入し過ぎも相手の尊厳を損なうので、相手の気持ちにしっかりとアンテナを張り人間関係をつくるという姿勢が大切だと思っています。
※福祉住環境コーディネーターとは
高齢者や障がい者に対し、できるだけ自立していきいきと生活できる住環境を提案するアドバイザーのこと。段差を解消する方法や手すりを取り付ける場所・良い取り付け方など福祉的観点から住みやすい環境をコーディネートします。