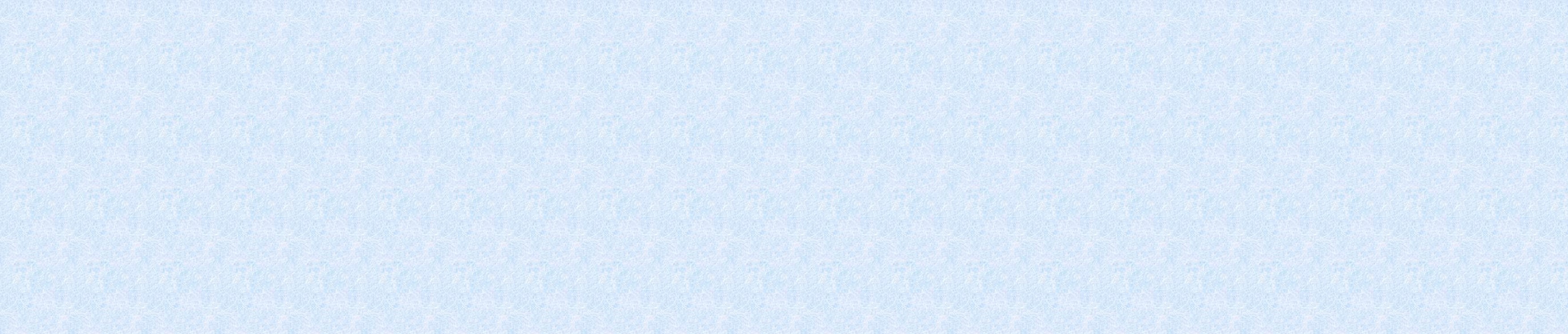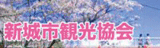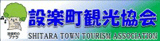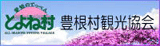本文
【奥三河探訪】神々が宿る作手
新城市作手地区について
新城市作手(つくで)地区(旧作手村)は、木曽山脈、美濃三河高原の南端に広がり、愛知県の東部にあります。平均標高は550メートに達し、豊川流域の平野部から急激に隆起している地形で、通称、作手高原と呼ばれています。
ちなみに、「作手」地名起源は諸説ありますが、その1つに、鎌倉時代に米福長者なる人物が現在の作手地区に、広大な土地を開墾し、地子・公事(中世の頃の地代と税金のこと)を納めて作手権(田畑を耕作する権利のこと)を得たところから呼ばれるようになったという説があります[1]。
ジルイと神々
東三河の山間地域には、ジルイ(地類)と呼ばれる、一種の同族組織が広域に分布しており、ジルイが単位となってジノカミ(地の神)と呼ばれる神祠を建て、共同で祭祀を行っている例が見られます[2]。
ジノカミといった村の小祠は明治末期から進められた神社合祀によって失われたり、氏神の境内に境内末社としてまとめられたりして個性を失ったものも多い[3]ですが、現在でも、作手地区では各家にジノカミやヤマノカミなどの神々を見ることが出来ます。
ジノカミ(地の神)
屋敷内の守護神として、大部分の家庭には宅地の北側辺りにジノカミをお祭りしています。石の祠、自然石に手を加えて「地神」と彫られているものなど形は様々です[4]。ジノカミを作る際には、密教系の祈祷師であるホウエンサマ(法印様)に依頼して、お性根を入れてもらいます。作手地区のジルイが祀るジノカミは同族神であると同時に、土地や屋敷地の神としての性格も色濃くあり[5]、今でも作手地区の人々から信仰されています。

(新城市作手地区S家のジノカミ、自然石のままで祭られている。)
ヤマノカミ(山の神)
ヤマノカミは山村で生活する人々に厚く信仰されてきました。ヤマノカミは自然石に手を加えて、「山之神」と彫られたものが多く、集落から近い里山の道の辻や、山道のわきや、小高い山の峠あたりに安置されています。

(新城市作手地区S家のヤマノカミ、巨石の上に「山之神」と書かれた石がある。)
おわりに
作手地区には他にも、風神様・田の神・水神様など多くの石の祠、自然石が街道沿いに多く安置されています。今でも、これらの神々は作手地区の人々を見守り続けており、正月になると、作手地区の人々は注連縄・お餅・橙などのお供え物をもって神々にお参りにいくそうです。