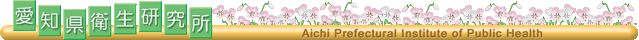東日本大震災後の放射性物質測定について
2011年9月15日
はじめに
2011(平成23)年3月11日に起きた東日本大震災によって東京電力福島第一原子力発電所が損傷し、放射性物質が発電所の外部まで漏れる事故が起きました。
私たちは日常生活において宇宙線や大地からの自然放射線を受け、食べ物からも自然界の放射性核種が体内に入ってきます。また、健康診断時のX線撮影などでも、少量の放射線に曝露されます1)。
しかし、今回の事故で人工の放射性核種が大気中に大量に拡散したため、厚生労働省は平成23年3月17日付け「放射能汚染された食品の取り扱いについて」2)において、食品中の放射性物質について暫定規制値を設定しました。対象とした核種は、放射性ヨウ素、放射性セシウム、ウラン、プルトニウム及び超ウラン元素のアルファ核種です。食品安全委員会はこれらのうち、主に放射性ヨウ素と放射性セシウムを測定すべきとの見解を示しました3)。また、環境省は同6月24日付け「水浴場の放射性物質に関する指針について」4)において、水浴場水の放射性セシウムと放射性ヨウ素に係る今夏の水質の目安を示しました。
事故発生後6ヶ月が経過した現在も、汚染されたワラを与えられた牛の肉が市場に流通するなど、連日、放射能汚染に関連する報道が続いています。
ここでは、現在当所で実施している放射性物質測定について解説します。
放射能と単位
放射線を出す物質を放射性物質といい、放射線を出す能力を放射能といいます。
放射能の強さは1秒間に原子核が崩壊した数で表され、その単位がベクレル(Bq)です。1秒間に1個の原子核が崩壊すると1 Bqになります。また、放射能が半分に減るまでの時間を半減期といい、核種により異なります。
一方、人に対する影響はシーベルト(Sv)で表します。放射線の種類や放射線が当たる組織ごとに人体に対する影響や感受性が異なるため、種類や組織ごとに定められた係数5)で補正することによって、全身への影響を表したものです。
500 Bq/kg × 1 kg × 1.3 × 10-5 mSv/Bq※ = 0.0065 mSv となります。
※ 実効線量係数(mSv/Bq)といい、ベクレルからシーベルトに変換する係数で、核種、化学形、摂取経路により数値が違う。mSv(ミリシーベルト)はSvの1/1000
放射性物質の測定
固体や液体中の放射能を測定する機器には、シンチレーション検出器と半導体検出器があります。
シンチレーション検出器は、検出器が放射線から受けたエネルギーを蛍光として放出する現象を利用したもので、発光した数から放射線の強さ、発光強度からエネルギーを測定できます。持ち運び可能な小型のシンチレーション検出器は、測定対象核種を絞った簡易測定に適しています。
半導体検出器は、放射線が検出器に入ると放射線のエネルギーに応じた電気信号が作られ、その信号をカウントすることで放射線の強さを測定しています。核種ごとにエネルギーが違うので、多数の核種を同時に測定することができます。シンチレーション検出器と比べてエネルギー分解能が高く、核種の区別が容易で、低いレベルまで測定できます6)。
当所では、厚生労働省及び環境省により暫定規制値等が設定された、放射性ヨウ素(ヨウ素131)と放射性セシウム(セシウム134、137)をゲルマニウム半導体検出器により測定しています。
県内の水道水や海水浴場水、県内を流通する食品中の放射性物質の測定結果は、愛知県のホームページで随時、公表しています。

参考文献
- 1)日本アイソトープ協会編 『改訂版 放射線のABC』 丸善(2011)
- 2)「放射能汚染された食品の取り扱いについて」 (平成23年3月17日 食安発0317第3号)
- 3)『「放射性物質に関する緊急とりまとめ」の通知について』 (平成23年3月29日 府食第256号)
- 4)「水浴場の放射性物質に関する指針について」 (平成23年6月24日 環水大水発第110624001号)
- 5)「放射線を放出する同位元素の数量等を定める件」 (平成12年科学技術庁告示第5号)
- 6)飯田博美編 『初級放射線(第7版)』 通商産業研究社(2005)