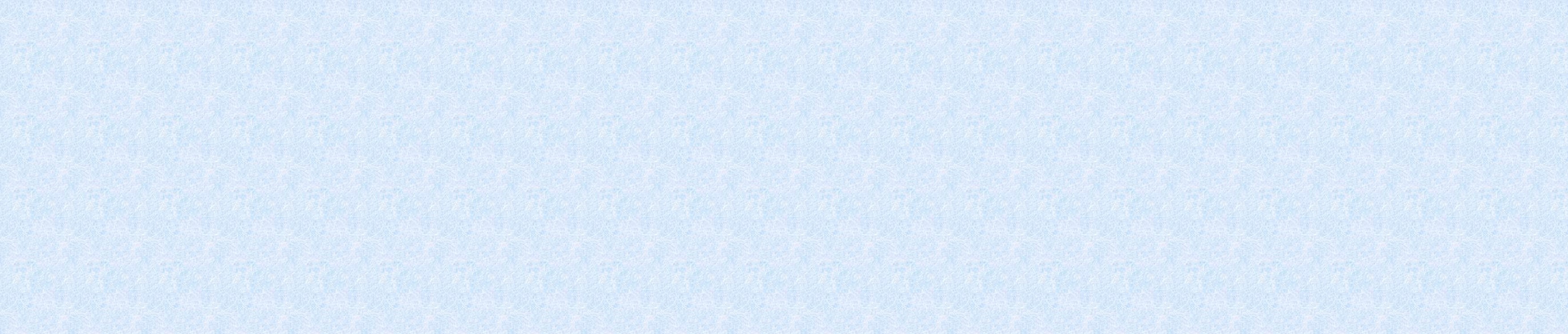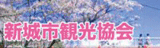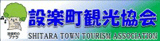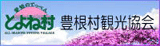本文
【奥三河探訪】第2回富山風土記~暮らしの中の伝統~
はじめに
北設楽郡を中心とする奥三河地域は、古来、多くの民間宗教者が活動してきた地域であり、その影響もあって様々な年中行事が培われ、現在でも豊富な伝承を誇っています[1]。今回の奥三河探訪「富山風土記」では、旧富山村で継承されてきた年中行事の中でも年の神の去来を強く意識した正月行事、特にモチイの正月行事を見ていきます。
(天竜川沿いにそびえる旧富山村の写真。)
モチイの正月
正月は年の神を迎えて祭る期間といわれています。古い時代の行事は旧暦で行われていたため、歳神様は新月である大晦日の夜に訪れ、一般に大正月と称される正月三が日を中心に祭られました。一方で、正月にはその年の農事が滞りなく進むよう前祝いの行事が行われ、これは満月(望月)の日である15日正月を中心に展開されていました。この15日正月を小正月、三河地域ではモチイ(望)の正月と呼んでいます[2]。
ニュウギ
モチイの行事に用いられる木製の飾りもので、ニンギともいいいます。愛知県から静岡県にかけての呼称で、長野県南部から愛知県にかけてはオニギ(鬼木)ともいい、モチイの正月が済むと、薪として燃やしてしまいます[3]。
旧富山村では、樫の木を割りニュウギを作ります。2本1対で、片方にだけ、平年なら「十二月」、うるう年なら「十三月」と書きます。後述のハナクイを立てている家では、3尺(約1m)の長さの「オオニュウギ」をいくつも作り、ハナクイの下部に立てかけます。

(オオニュウギに十二月書きを行っている最中の写真)
オオニュウギに対して、5、6寸(約15cm)ほどの「コニュウギ」も作ります。旧正月1日早朝には、コニュウギを持って、先祖の墓や無縁仏の墓などに参り、コニュウギを供えて拝みます。この行事は「ムショマイリ」と呼ばれるお参りの一種で、どんな墓でも無性に参ってしまうので、ムショマイリなのだと旧富山村ではいわれています。

(コニュウギの写真)
この「十二月」を新年の薪に書き込む行事は三河地域で広く行われていますが、由来は定かではなく、昔の月々の吉凶を占った名残ではないかとの説もあります[4]。
江戸幕府の文献では、「ニン木という物あり。」、「二つに割たるを一対とす」とあり、少なくとも江戸時代から続いている行事であることが伺えます[5]。
ハナクイ(ハナクギ)
他の地域では、ハグイ(葉杭)、ミヅクイ(瑞杭)とも呼ばれ、年の神を祭る高い柱のことをいいます[6]。旧富山村ではハナクイ(ハナクギ)と呼ばれ、現代の門松にあたるものです。
ハナクイは樫の木2本を用いて、松、榊、竹、注連縄でもって飾りつけを行います。
作り方は、南向きとなるように、家の前の地面に、それぞれ6尺(約2m)ほどの樫の木を差し、この2本の杭の下部に、2本の棒を渡して結びます。
(ハナクイの作成場面の写真。地面がコンクリートのため、砂を入れたバケツに杭を差しているが、本来であれば地面に差す。)
さらに、松と榊で飾りつけ、2本の杭の間に、「マメンボシ」と呼ばれる、竹枝の先端に直径約1cm、長さ約15cmほどの皮付きのフシノキ(別名:ウノハナ、ウツギ(空木))をたくさん挿しこんだ竹2本をクロスするように縛り付けます。これはフシノキを稲穂に見立て、豊作を祈って稲穂が実った様子を表したものです[7]。旧富山村では、このマメンボシを農家のハタバシラ(稲木、はざ木のこと。収穫した稲を干しているところを旧富山村ではハタバシラという。)をまねたものだといわれています。

(フシノキを竹の枝に挿している作業中の写真)
次にシメケイダレと呼ばれる、4つの吉田流の紙垂をつけた右縄の注連縄を二本の杭の間にかけて、下部に渡した2本の棒の上にタワラ(俵)と呼ばれる3つの樫の木を藤の蔓で縛ったものを2個置き、ハナクイの正面と裏面にニュウギを立てかけて完成です。

(タワラの写真。藤の蔓で3本の丸太を縛る。)
(ハナクイにオオニュウギを立てかけた写真。)
旧富山村のモチイの正月飾りはこのとおりですが、これら飾りは形を変えて奥三河各地で伝わっています。しかし、少子高齢化などの影響で、現在は行っている家も少なくなっているのが現状です。
おわりに
奥三河地域では、数多くの正月の伝統行事が行われてきました。他にも、山の講、秋の神送り・神迎え、畑作の収穫儀礼などに奥三河独自の行事の姿が伝えられています[8]。
参考文献
[1] 愛知県史編さん委員会「愛知県史 別編 民俗3三河」、2005年、649頁
[2] 愛知県史編さん委員会「愛知県史 別編 民俗3三河」、2005年、652頁
[3] 加藤友康、高埜利彦、長沢利明、山田邦明「年中行事大辞典」吉川弘文館、2009年、536頁
[4] 柳田国男「歳時習俗語彙」民間伝承の会、1939年、42頁
[5] 中山太郎「諸国風俗問状答 : 校註」東洋堂、1942年、193頁
[6] 柳田国男「歳時習俗語彙」民間伝承の会、1939年、32頁
[7] 愛知県史編さん委員会「愛知県史 別編 民俗3三河」、2005年、669頁
[8] 愛知県史編さん委員会「愛知県史 別編 民俗3三河」、2005年、649頁