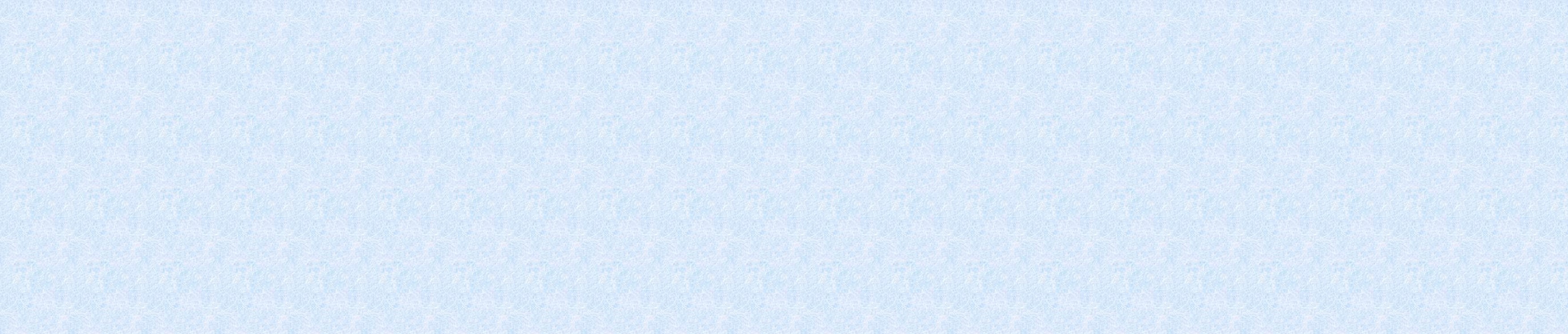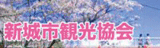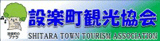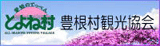本文
【奥三河探訪】富山風土記~富山の村を訪ねて~
奥三河探訪は、今までより更に探訪にフォーカスし、奥三河地域のマニアックな部分について紹介していきます。
季節の情報やイベントについては、新城設楽振興事務所公式Instagramまで!
旧富山村の歴史と概況
豊橋駅から電車で揺られること約3時間、長いトンネルを抜けると赤レンガのレトロな建物が特徴の大嵐(おおぞれ)駅が見えてきます。
東海旅客鉄道(JR東海)飯田線の秘境駅「大嵐駅」、三方は1000m級の急峻な山々に囲まれ、前面は佐久間ダム湖を一望の下に収めることが出来るこの駅から、さらに村営バスで行くこと10分ほど。かつて「日本一小さい村」として有名だった隠れ里、旧富山村(現・豊根村富山)に到着します。
(富山の最寄り駅「大嵐駅」。東京駅をモチーフにした建物は、平成9年に旧富山村が休憩所として建てたもの。休憩所内には旅のノートがあり、ここを訪れた人たちの思いが綴られています。令和7年1月26日撮影)

(村営バスの富山線の写真。1乗車200円で大嵐駅から旧富山村に行くことが出来ます。
一部時間帯は予約制のため注意が必要。令和7年2月19日撮影)
旧富山村(以下、「富山」と言う)は平成17年に愛知県豊根村と合併した、愛知県の東北端、長野県・静岡県の県境に位置する、奥三河で最も山深い場所にあります[1]。
面積の95%以上は森林に覆われ[2]、天竜川随一の渓谷故に、村の平均傾斜角度は30度以上[3]もあるような険しい土地であり、人が安易に住めるような場所ではありません。
が、ともかくも富山の先人たちはここに住むことにし、山を切り開き、石垣を積んで平地をつくり、土を耕して畑を拓きました。
村人の手が加わっていない平地は皆無と言っていいほどです[4]。
この僅かながらの平地は、富山の人々の血と汗と涙なくしては語れません。

(山々に囲まれ、ひっそりと佇む富山。「うばのふところ」とも呼ばれる特徴的な地形で、愛知県の近隣に比べて温暖な気候[5]。1月でもミカンが実るほどで、冬でも過ごしやすい。令和7年3月1日撮影)
この奥地に、しかも豊かに暮らすことのできない場所を選んでなぜ村が拓かれたのか。
理由は定かではありませんが、近代の文献『田辺氏家伝年代記』はその訳を「斯る乱世に身を忍び、名を隠す人々の栖には上々の所なり」との記述があります。
富山の地は、それぞれの思いを秘めて、世を忍ぶ人達が生きる隠れ里だったのかもしれません。
故きを温ねて~田舎暮らし塾~
この隠れ里では、様々な行事が行われています。今回は、その中の一つ「田舎暮らし塾」について紹介します。
「田舎暮らし塾」は、一般社団法人とみやまの里が主催の地域活性化イベント。
令和6年度は5回の日程があり、回ごとに体験できる内容は、蜂蜜絞り、栃の実拾い、ゆずジャム作り、猟師体験、こんにゃく作りと富山の特産品を活かしたものばかり。
塾生は、興味がある体験に応募し、富山の暮らしについて学ぶことが出来ます。
デジタルデトックスにもってこいの体験です。
詳しくは、とみやまの里HPへ
(令和6年度「田舎暮らし塾」の参加者と伝統的な門松である入木(にゅうぎ)。富山の神秘的な魅力に惹かれて、複数の回に参加している人も。令和7年1月28日撮影)
(奥三河探訪「富山風土記」はシリーズとして、数回に分けて旧富山村の魅力について伝えていきます。)