本文
2025年度「学校安全緊急情報共有化広域ネットワーク」活用訓練結果を報告します
2025年度「学校安全緊急情報共有化広域ネットワーク」活用訓練結果を報告します
県教育委員会では、2005年12月に「学校安全緊急情報共有化広域ネットワーク」を構築し、緊急情報の迅速かつ広域的な共有と地域ぐるみで子どもを守る体制づくりを推進してきました。
さらに、2008年7月には、運用ガイドラインを策定し、伝達する情報の基準や伝達範囲・方法を明確に示すとともに、市町村教育委員会を中心とした新たなネットワーク(以下「市町村ネットワーク」という。)による運用を、同年9月から開始したところです。
去る5月29日(木曜日)に、この市町村ネットワークによる情報伝達の検証と、地域における安全確保体制の更なる整備の促進をめざして「学校安全緊急情報共有化広域ネットワーク」活用訓練を実施しました。この度、この訓練結果がまとまりましたので、お知らせいたします。
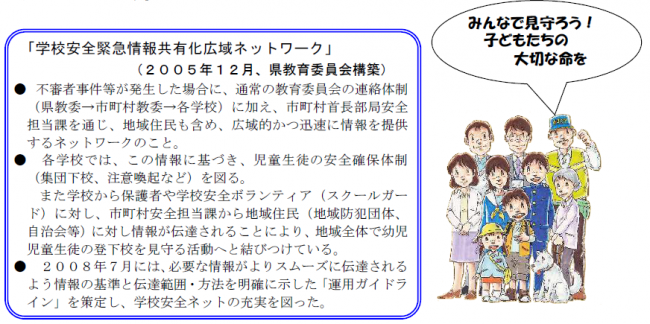
1 訓練の概要
(1)訓練の方法
◇ 2025年5月29日(木曜日)午後1時ごろ、県内8警察署から8市町教育委員会へ訓練緊急情報を発信
◇ 連絡を受けた8市町教育委員会は、市町ごとのネットワークにより、市町内全ての学校や幼稚園・保育所、関係部局及び近隣の市町村教育委員会※1へ情報発信
豊山町→6市へ 江南市→6市町へ 蟹江町→6市村へ 南知多町→2町へ
知多市→4市町へ 西尾市→6市町へ 豊田市→12市町へ 豊橋市→4市へ
※1 市町村教育委員会ごとに作成した「市町村ネットワーク図」に記載されている原則として隣接している市町村の教育委員会
◇ 8市町教育委員会から情報を受信した市町村教育委員会は、市町村内全ての学校や幼稚園・保育所、関係部局及び情報が届けられていない近隣市町村教育委員会へ情報発信(→ これにより県内全ての市町村教育委員会が訓練情報を受信)
(2)訓練の対象校 *事後調査における有効回答
《県内の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、特別支援学校、中等教育学校、保育所等》
(3)訓練の内容
ア 市町村ネットワーク図に基づく情報伝達
イ 学校等の実情に応じた行動訓練
2 訓練の結果
(1)情報受信時刻
(2)情報伝達に合わせた訓練の実施状況
<主な内容>
・ 教職員による校内外の巡回
・ 校門の施錠
・ 幼児児童生徒への下校時の注意喚起
・ 保護者へのメール一斉配信訓練
(3)成果
〇職員が少ない中で情報発信を行ったが、それぞれの役割を責任を持って担当することが出来た。声を掛け合いながら、確認し合うなど、連携が取れていた。昨年度の反省を活かし、電話連絡やFAXを送る順番を見直したことで、迅速に対応ができた。
〇市に情報が到着してから保育所への伝達するまでの伝達経路を確認・実践することが出来た。FAXとメールの2種類の方法で情報伝達することにより、施設への情報伝達の確実性を向上させた。
〇緊急情報が入ってからの対応訓練を行い、子どもの意識を高めることが出来た。また、携帯メール配信を行い、保護者そして地域ボランティアの方に協力していただき、見守り活動を行うことが出来た。
〇事前に事務方にも周知の上、最速で高校管理職まで情報が伝達されて、学校全体に周知されるまでどれくらいかかるかを確かめた。
〇今回は、「メール受信」→「事務」→「管理職」→「生徒指導部長」という連絡体制を確認した。
(4)課題
〇FAXによる情報伝達は迅速さに欠けるため、他の有効な手段の検討が必要。メールでは届いたことに気付きにくい点も課題。
〇担当者が不在の場合、これほどの作業をこなすことが難しいため、伝達方法の簡略化やデジタル化の検討が必要。
〇ネットワーク図が理解しづらく、担当者の勘違いによって情報が届かない施設が多くあった。
〇訓練に関する事前通知が確認できず、当日の訓練に参加できなかった学校があった。職員間の体制や施設内の環境を整備する必要がある。
〇園児の降園時間と重なるため、別の機会に防犯訓練を実施予定。
〇不審者情報の発信後、保護者の確認率が65%であり、全員の確認が今後の課題。
(5)対策
今後も、関係機関に、ネットワーク図の理解と伝達方法の周知徹底を図るよう働きかけ、毎年1回の訓練を継続して実施していくことにより、幼児児童生徒の安全確保のため、緊急情報がより円滑に伝達できる工夫を重ねていく。
2025年度「学校安全緊急情報共有化広域ネットワーク」活用訓練結果 [PDFファイル/481KB]
教育委員会事務局 保健体育課
安全グループ
担当:佐々木・野澤
内線:3925・3926
ダイヤルイン:052-954-6829
E-mail:hoken-taiiku@pref.aichi.lg.jp

