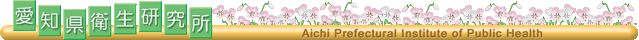病原大腸菌 -下痢を起こす5種類のメンバー
大腸菌は、健康なヒトの大腸内で生息し、また環境中にも広く分布している微生物ですが、腸管出血性大腸菌O157などのように、ある種の大腸菌はヒトに下痢、腹痛などといった病気を起こします。このような、胃腸炎を起こす大腸菌を“病原大腸菌”あるいは下痢原性大腸菌と呼んでいます。
また、病原大腸菌は、一般的には5種類に分けられています。ここでは、これら病原大腸菌の性質や症状などを説明するとともに、病原大腸菌による食中毒の発生状況や病院での検出状況をお知らせします。

病原大腸菌の発見
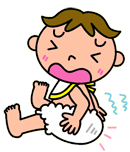
大腸菌1)の中には下痢を起こすものがあります。これらを‘病原大腸菌’もしくは‘下痢原性大腸菌’と呼んでいます。大腸菌がヒトの下痢症の原因となることを始めて報告したのは、1927年のAdam(アダム)が最初と考えられています。その科学者は、胃腸炎を起こしている乳幼児の大便の中からいくつかの大腸菌を分離し、いろいろな種類の糖と混ぜて培養し、どの糖を栄養として利用するかを調べました。そして、下痢をした多くの乳幼児の大便中に含まれる大腸菌のうち、いくつかの決まった糖を利用するただ1種類の大腸菌が下痢症を起こすと推測しました。
次いで1933年、Goldschmidt(ゴールドシュミット)が胃腸炎の乳幼児から分離された大腸菌に①血清学的な特徴があること、②その大腸菌が胃腸炎乳児の約半数から分離されても健康な乳児や成人からはほとんど分離されないこと、③ヒトからヒトに感染して病気を起こすという重要な発見をしています。
1940年代に入り、イギリス国内の病院では乳児下痢症が流行したことから、大腸菌と下痢症との関連性が注目されはじめました。そして、患者と健康者との比較研究や血清型別分類法2)の開発、動物や遺伝子技術を使った研究が活発に行なわれたことにより、胃腸炎を起こす大腸菌が確かに存在すること、そして下痢発症のしくみが明らかになってきました。
- 1)大腸菌の学名はEscherichia coli (エシェリヒア・コリ)といい、短くE. coli (イ-・コリ)とも呼んでいます。
- 2)特定の大腸菌にのみ反応する免疫血清を用いた大腸菌の分類方法。
5種類のメンバー
1) 腸管病原性大腸菌(EPEC)
5種類の病原大腸菌のうち、腸管病原性大腸菌(enteropathogenic E.coli、略してEPEC)は最初に見つかりましたが、下痢を起こす仕組みが分かったのは近年になってからでした。
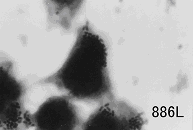

1979年に、Cravioto(クラビオト)らはEPECをヒトのHEp-2細胞3)と混ぜて培養すると、写真1のように細胞と比べて非常に小さな多数のEPECが細胞表面の一角に丸く集まって接着(局在接着)することを発見しました。
この現象をよく調べた結果、EPECは菌の表面の接着物質(凸)4-1)と細胞の表面の受容体(凹)4-2)とがピッタリくっ付くことにより細胞に接着していることがわかりました。しかも、その受容体(凹)は、EPECが持っている微小な注射器のような管4-3)を通してEPEC自身が細胞側に送り込んだEPECの作った物質であることもわかりました。
そしてヒトの体内では、小腸に入ったEPECがあたかも船が海底に錨(いかり)を降ろすようにしっかりと粘膜細胞に接着し、粘膜細胞上に密生する栄養を吸収する働きのある微絨毛(びじゅう毛)を壊して下痢を起こします。
EPECは、2歳以下(特に6ヶ月以下)の子供に感染者が多く、発展途上国では乳幼児下痢症の原因の30~40%もがEPECであるとの報告があります。わが国においても、乳幼児の下痢症から散発的に分離されているだけでなく、時には集団食中毒も起きています。
下痢になったとき、粘液便の排せつや水様便が大量に出て脱水症状を引き起こすことがあります。健康な大人にとっては“たかが脱水”かも知れませんが、乳幼児には重篤な症状を引き起こすことが少なくなく、非常に注意すべき症状です。また、腹痛やおう吐、軽度の発熱を起こしたり、体がだるいなどの症状が現れたりします。潜伏期間は多くは12~24時間5)です。治癒期間は、一般に乳幼児では1週間くらいまで6)、成人は1~3日くらいで回復します。
- 3)HEp-2細胞は、ヒトの喉頭癌(こうとうがん)に由来する培養細胞です。
- 4-1)Intimin (インチミン)、4-2)Tir(ティア)、4-3)Ⅲ型分泌装置と呼ばれています。
- 5)3日後あるいはもう少し後に発症する場合もあります。
- 6)21~120日と長引いたとの記録もあります。
2) 腸管組織侵入性大腸菌(EIEC)
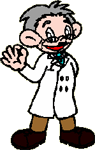
この病原大腸菌は、1969年に国立予防医学衛生研究所7)の坂崎利一博士によりはじめて報告され、腸管の粘膜組織中に侵入することから、腸管組織侵入性大腸菌8)(enteroinvasive E.coli、略してEIEC)と呼ばれています。
EIECは、重症な大腸炎を起こすことで知られる赤痢菌によく似た性質をもち、赤痢菌と同じように大腸の上皮細胞の中に侵入し、増殖しながら周囲の細胞にも広がり、大腸や直腸に潰瘍(かいよう)性の炎症を起こします。
EIECは、乳幼児に感染することはまれです。また、その発生は散発的なことがほとんどですが、過去には大きな集団例も発生しています。EIECの潜伏期間は19)~5日間(多くは3日以内)で、患者は、しぶり腹10)を起したり、血液、粘液、あるいは膿(うみ)をまじえた下痢を起こします。その他に、発熱、はき気、おう吐、けいれんなどの症状が現れることが多く、寒気、頭痛を伴うこともあります。これらの症状は、長引く場合もありますが多くは2~3日で治まります。
- 7)現在の国立健康危機管理研究機構。
- 8)腸管侵襲性大腸菌とも呼ばれています。
- 9)8時間で発症する例もあります。
- 10)トイレに行った後でも、何度もトイレに戻り、だんだん粘液だけが排泄されるようになります。
3) 腸管毒素原性大腸菌(ETEC)
この病原大腸菌は、腸管内で下痢の原因となる毒素を産生することから、腸管毒素原性大腸菌(enterotoxigenic E.coli、略してETEC)と呼ばれています。
ETECは、1967年に子ブタの下痢症の原因菌として発見され、ヒトの病原菌としては、インドで下痢症を調査していたSack(サック)らにより1971年に報告されました。
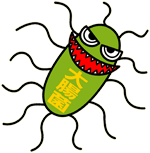
ETECは、大規模な食中毒あるいは海外旅行者下痢症の原因となることの多い病原大腸菌です。特に、東南アジアやアフリカなどの上下水道が十分整備されていない国々へ旅行する方は、ETECなどの下痢を起こす微生物に感染することが多いので、旅先では水道水を口にしない、生の野菜や前もって皮の剥いてある果物は避けるなど、飲食に対する注意が必要です。
症状は、水様性の下痢を伴うことが多く、ひどい場合には、大便がコレラ患者のように ‘米のとぎ汁様’になり脱水症状を起こします。腹痛、おう吐を伴うことが多く、発熱はあまり起こりません。潜伏期間は、多くの場合1211)~72時間ほどです。回復期間は、1~3日で回復する場合から10日以上と長引く場合もあります。
- 11) 8時間と短い場合もあります。
4) 腸管出血性大腸菌(EHEC)
この病原大腸菌は、血液が混じった下痢を起こすことから、腸管出血性大腸菌(enterohemorrhagic E.coli、略してEHEC)と呼ばれます12)。
EHECはEPECに似た接着作用によって大腸に定着し、'ベロ毒素'と呼ばれる強い毒素を放出して腸管が水分を吸収できなくしたり血管を破壊したりします。EHECが世界的に注目されたきっかけは、1982年に米国のオレゴン州とミシガン州で発生したハンバーガー食中毒事件です。真っ赤な下痢便から今では有名なO157が検出されました。わが国では1996年に大阪府堺市で小学生を中心としたO157集団事例が発生し、散発例を含めて1年間に全国から17,877名の患者が報告され、12名が亡くなりました。最近10年間の我が国の腸管出血性大腸菌感染症届出数(患者及び無症状病原体保有者を含む)は年間3000~4000名です。O血清型ではO157が最も多く、次いでO2613)、O111とO121が続きます。
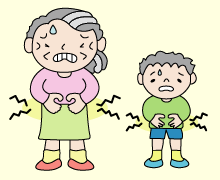
症状は、腹痛と水様性の下痢で発症し、翌日に血便を呈することが多いようです。おう吐は少なく、発熱は37℃台と軽度です。潜伏期間は、一般的に3~5日ですが感染後10日以降発症した例もあります。平均8日で回復するとされていますが、一部の患者ではHUS14)といわれる腎臓などの障害を引き起こし重症化・遷延して死亡することもあります。特に小児や高齢者はHUSを発症する割合が比較的高く、重症化しやすいようです。
2011年4月に焼肉チェーン店を原因施設とする腸管出血性大腸菌O111集団食中毒が発生し、5月9日現在富山県と福井県で合わせて4名の方が亡くなっています。わが国におけるEHEC O111感染症の届出は、2007年以降年間100名前後ですが、死亡例の報告は、1986年松山市内の乳児院入所者1名のみでした。O111集団事例は2000年から2009年の間に幼稚園、保育所、学校等で12例の報告があります。 また、2008年8月に米国オクラホマ州で発生した患者数341名のO111集団事例では、O111感染が確認された156名中26名がHUSを発症し、1名死亡しています。
O111の特徴としてリジン脱炭酸反応陰性、運動性陰性株が多い15)ことがあります。
腸管出血性大腸菌はO血清型に関係なく熱に弱く75℃、1分以上の加熱で死滅するので、家庭での予防策としては食肉の十分な加熱(特に小児、高齢者、抵抗力の弱い人)16)、手洗いが有効です。また下痢、腹痛、血便等の食中毒の症状が認められる場合は直ぐに医療機関を受診することが大切です。
- 12)EHECは、この大腸菌が産生するベロ毒素の名前からベロ毒素産生性大腸菌(verotoxin-producing E.coli:VTEC)、あるいはベロ毒素が赤痢菌の毒素である志賀毒素に類似していることから、志賀毒素産生性大腸菌(Sigatoxin-producing E.coli: STEC)とも呼ばれています。
- 13)Hiramatsu R et al. Characterization of Shiga toxin-producing Escherichia coli O26 strains and establishment of selective isolation media for these strains. Journal of Clinical Mibrobiology. 40(3):922-5, 2002.
- 14)溶血性尿毒症症候群(EHEC感染に続いて起こる腎臓障害や中枢神経症状)。
- 15)山崎貢他。リジン脱炭酸反応陰性の腸管出血性大腸菌血清型O111による集団発生事例―愛知県 病原微生物検出情報29(9):256-257, 2008.
- 16)厚生労働省 食安監発第0514001号 平成19年5月14日 「飲食店における腸管出血性大腸菌食中毒対策について」
5) 腸管凝集接着性大腸菌(EAggEC)
腸管凝集接着性大腸菌17)(enteroaggregative E.coli、略してEAggEC)は、1987年にNataro(ナタロー)らが南米チリの小児下痢症患者から見出した病原大腸菌であり、最も新しい種類の病原大腸菌です。EAggECは、実験的に培養したヒトの細胞表面ばかりでなく培養容器にも接着する特徴があり、写真2のように菌が集まって 接着(凝集接着)18)することから、その名前が付けられました。
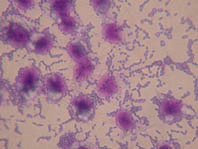
EAggECは、南米やアフリカなどの発展途上国の乳幼児下痢症から多く検出されています。しかし、先進国においてもEAggEC感染症は発生しており、国内では、東南アジアから帰国した下痢患者からだけでなく、乳幼児下痢症、食中毒などの集団事例19)からもEAggECが検出されています。
症状は、一般に粘液を含む水様性の下痢便が出て、ときには血液が混ったり緑色になったりします。また、腹痛を起こすことが多く、吐いたり、38℃台に発熱することもあります。潜伏期間は、一般的に7時間~2日程度です。回復期間は3~7日程度ですが、乳幼児や免疫力が低下している場合は長くなる傾向があり、持続性(2週間以上)下痢を起こす場合があります。
- 17)腸管集合性大腸菌とも呼びます。
- 18)菌によっては、‘積み上げたレンガ’のような、あるいは ‘蜂の巣’状に接着します。
- 19)EAggECが原因菌と推定された集団下痢症事例が、1993年に岐阜県、1999年に秋田県、それに、2000年に大阪市から報告されています。また、愛知県が過去にさかのぼって調査したところ、1989年に長野県へ修学旅行に行った中学生がこのEAggECによる食中毒に罹っていたことが強く推察される事例がありました。
食中毒の発生は?

我が国における食中毒の発生件数は、1998年~2003年の6年間では年平均2,200件ほどで、うち細菌性のものが約80%(1,800件)、ウイルス性が約10%(200件)、残りは自然毒などや不明事例でした。
細菌性食中毒のうち、病原大腸菌による件数は、2001年までは年平均約240件(EHEC 16件を含む)で、サルモネラ属菌(620件)、腸炎ビブリオ(560件)、カンピロバクター(490件)に次ぐ第4位を占めていました。
しかし、なぜか2002年には96件、また2003年には47件と減少し、第5位(59件の黄色ブドウ球菌と交代)に後退しました。一方、病原大腸菌食中毒の1事例あたりの患者数については、2001年までは平均12名(9~14名)でしたが、2002年には18名、2003年には30名(ウエルシュ菌83名に次ぐ第2位)と増加しています。
また、病原大腸菌は大規模な食中毒などの集団発生事例をしばしば起こしており、1993年には岐阜県内でEAggECによる幼稚園児と小中学生の患者2,697名の事件が、また1996年には先に記載したようにEHECのO157による小学生を中心とした事件が発生しています。したがって、現在は病原大腸菌食中毒の発生件数が減少していますが、病原大腸菌が危険性の高い病原菌であることは変わらないと考えられます。
なお、発生件数等の詳しい情報は、厚生労働省のホームページ(食中毒・食品監視関連情報)をご覧ください。また、愛知県内の発生件数は、愛知県保健医療局・生活衛生部・生活衛生課のホームページ(愛知県の食中毒発生状況)に示されています。
病院ではどのくらい検出されているか?
愛知県衛生研究所では、本県内の特定の1病院の検査室と共同で、小児や成人の下痢症患者の大便から分離され、病原性があると推定された約1,700株の大腸菌の病原性を調べてみました。
その結果、約87%もの大腸菌は腸管内の普通の大腸菌と区別できませんでしたが、残りはEPEC(病原性大腸菌)4.9%、EAggEC(凝集接着性大腸菌)4.9%、EHEC(出血性大腸菌)1.7%、ETEC(毒素原性大腸菌)1.6%、及びEIEC(組織侵入性大腸菌)0.2%の割合で検出されました。
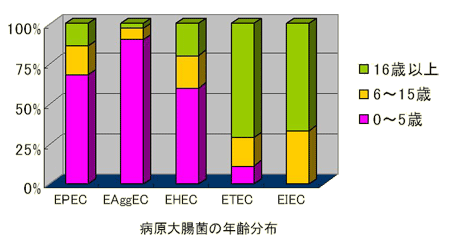
また、年齢分布については、グラフのように、検出された全ての菌株を100%とすると、EPECでは全体の68%が0~5歳から、18%が6~15歳から、そして14%が16歳以上から検出され、小児の患者ほど高率に見つかりました。EAggECについては、これらの年齢層での検出割合がそれぞれ89%、7%、4%と、EPECよりもさらに低年齢にその検出割合が集中していました。その他の病原大腸菌のこれらの年齢階層別分布については菌株数が少ない種類もありますが、EHEC(60%、20%、20%)、ETEC(11%、18%、71%)、及びEIEC(0%、33%、67%)のようになっていました。
病原大腸菌の中では最も新しい種類であるEAggECは、発展途上国において乳幼児下痢症の原因菌となっていると報告されています。しかし、ここにその結果を示した我々の検討から、EAggECは国内で多数検出されているEPECと同率(約5%)に検出されること、また、幼小児ほど高率に検出されること、が明らかとなりました。したがって、国内の幼小児にもEAggECによる下痢症が少なくないものと考えられます。
付録:病原大腸菌の血清型
大腸菌の血清型別分類法(1 病原大腸菌の発見の注釈2を参照)は、一般的にはO抗原とH抗原20)の組み合わせ(O:H血清型)により行ないます。今まで述べてきた5種類の病原大腸菌は、それぞれ特定のO:H血清型を示すものが多いのです。しかし、検出された大腸菌のO:H血清型が病原大腸菌に多くみられる血清型の一つと同じだからといって、その菌が病原大腸菌であるとは限りません。病原大腸菌であると決定するには、病原因子の検出が必要です。
例えば代表的なEHECの血清型であるO157:H7は、必ずしもEHECとは限らず、病原性のない普通の大腸菌の可能性もあるのです。それで、EHECと決めるために病院など多くの検査室では、まず検査が比較的簡単にできる血清型別分類法により篩(ふるい)にかけて、大腸菌の中から病原大腸菌と疑われる菌を選び出します。その後に、菌がベロ毒素(VT)を産生するか、あるいはその遺伝子を持っているか、を確認しています21)。
病原大腸菌のO:H血清型は非常にたくさんあり、これらを全て示すと非常に複雑になります。したがって、以下にO血清型のみについて代表的なものを示しました。
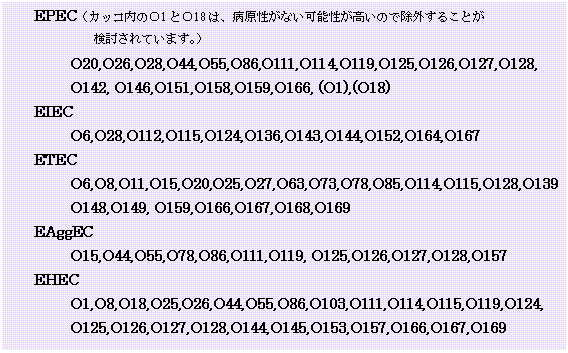
- 20) O血清型は、大腸菌が持っている自分自身と外界を隔てる壁(細胞壁)の血清学的な性質を現します。また、H血清型は、大腸菌の運動するための器官(べん毛)の血清学的な性質を現します。O血清型は約170種類、H血清型は57種類あります。
- 21)ただし、 O:H血清型に型別分類されない大腸菌であってもEHECが含まれている可能性もあることから注意深く検査を行なう必要があります。
おもな参考資料
- 坂崎利一編:新訂食水系感染症と細菌性食中毒、中央法規、2000年.
- 厚生省生活衛生局監修:食中毒予防必携、社団法人日本食品衛生協会、1998年.
- 三輪谷俊夫監修:食中毒の正しい知識、菜根出版、1993年.
- 竹田美文:大腸菌.臨床と微生物、1985年;12巻:p260―275.
- 竹田美文、三輪谷俊夫著:ビブリオ感染症-腸炎ビブリオ・コレラ菌・毒素原性大腸菌-、医師薬出版(株)、1982年.
- 坂崎利一編:食中毒、中央法規、1981年.
- Nataro.JP and Kaper JB:Diarrheagenic Escerichia coli Clinical Microbiology Reviews 1998;11:142-201 .
- Edited by Doyle:Foodborne Bacterial Pathogens.Macel Dekker inc.,New York,1989.