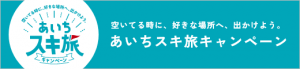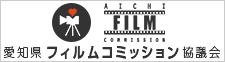ページの先頭です。
メニューを飛ばして本文へ
本文
愛知県観光コンベンション局
計画・施策等
統計・調査
各種手続
・観光振興に寄与する行事等に関する愛知県の後援名義使用申請手続
愛知の観光情報
施設の情報
パンフレット・写真
・パンフレット(Aichi Nowのガイドブックへリンクします)
・写真(Aichi Nowのフォトギャラリーへリンクします)
観光関連事業者向け事業
・観光関係者向けビジネス・サイト Aichi Now Biz
・旅行会社&メディア向け観光情報サイト Aichi Now Pro
観光コンベンション局の組織
※観光コンベンション局の事務分掌