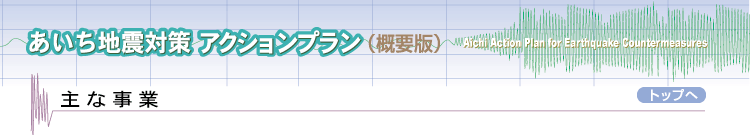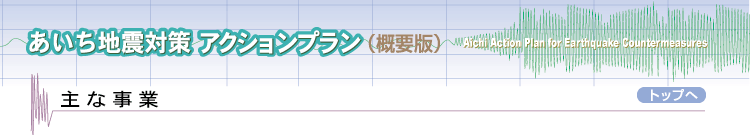|
 |
(1) |
防災協働社会の形成を目指して地震対策推進条例(仮称)を制定する。【「自助」、「共助」、「公助」の役割分担の明確化】
| ○ |
地震対策推進条例(仮称)の制定 |
|
大規模な地震による災害から県民の生命、身体、財産を守るため、県、市町村、事業者、県民がそれぞれの役割を果たしながら、一体となって大規模地震に対応していくことを明らかにする。 |
|
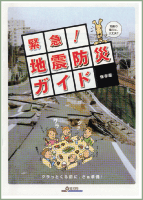
啓発リーフレット

あいち防災カレッジ

防災協働社会のイメージ
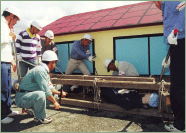
防災訓練
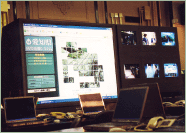
防災情報システム
|
| (2) |
県民、企業、自主防災組織、ボランティアなどの様々な主体による防災対策の自発的な取り組みの促進を図る。【「自助」、「共助」の推進】
| ○ |
様々な啓発方法による県民への意識啓発の継続的な実施
|
|
日頃から家庭内備蓄や家具等の転倒防止などを推進するため、パンフレット、ポスター、ビデオなど様々な方法により意識啓発を繰り返し行う。
|
| ○ |
あいち防災カレッジの開催とあいち防災リーダーのネットワーク化の推進 |
|
修了者は「あいち防災リーダー」として地域の防災リーダーの役割を努める。
毎年250人 5年間(H14〜H18)で1,250人
|
| ○ |
総合的な学習の時間を活用した「親子で学ぶ参加体験型地震防災教育」の実施
|
|
小学校4校区で実施する。
|
| ○ |
自主防災組織、消防団、ボランティア、NPOとの連携強化 |
|
防災ボランティアコーディネーターを養成する。
毎年200人(〜H15で目標1,000人養成終了)
自主防災組織実践的活動マニュアルを作成する。
|
| ○ |
事業所の防災対策の推進 |
|
| (3) |
全庁挙げての地震防災対策の体制づくりと関係機関との連携強化を図る。【「公助」の推進】
| ○ |
ロールプレーイング方式を採用した図上訓練の実施
|
| ○ |
市町村、ライフライン、その他防災関係機関との連携強化
|
| ○ |
市町村地震防災対策事業に対する支援
|
|
H14補助金創設
|
| ○ |
東海地震・東南海地震等被害予測調査の実施 |
|
想定地震4つ、発生時期3ケースで実施。H15中に全調査完了。 |
|
| (4) |
防災協働社会の前提となる防災情報の共有化を図る。
| ○ |
高度情報通信ネットワークの整備
|
|
H14.12地上系、H16.4衛星系運用開始
|
| ○ |
防災情報システムの構築
|
|
H14.12運用開始、H16.4GIS機能追加
|
| ○ |
ITを活用した情報提供体制の整備 |
|
防災ホームページの整備
避難所における情報管理の促進
テンプレート翻訳技術を利用した外国人向け防災
情報提供システムの構築の促進 |
|
|
|
|