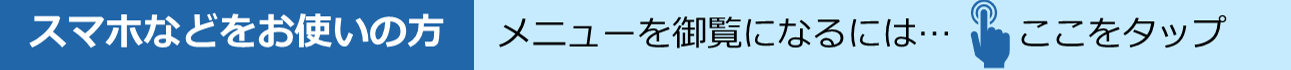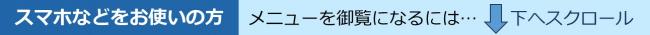ページの先頭です。
メニューを飛ばして本文へ
本文
ようこそ! 農総試へ
お知らせ
- 研究の成果「研究報告」に「第57号」を追加しました(2025年12月17日)
これまでの研究成果や開発した技術は、研究報告、研究短報、技術情報、動画、10大成果などで公開しています
- 研究室・室だよりの野菜研究室に日々の業務の一端を紹介するダイアリー第8報 を追加しました(2025年12月9日)
- 2019年10大成果「シマウシ」が第35回イグノーベル賞生物学賞を受賞しました(2025年9月19日)
- 共同研究実施者を募集中です
- 農業総合試験場では、家畜伝染病の防疫対策を実施中です
視察・見学などは、お受けできない場合があります
- 農業総合試験場では、現在長寿命化工事を実施中です
来場者に御不便をおかけする場合があります
新着情報
あいち農業イノベーションプロジェクト
愛知県農業総合試験場は、大学やスタートアップ企業等との共同研究体制の強化を図り、新しい農業イノベーション創出を目指す「あいち農業イノベーションプロジェクト」を実施しています。
関連リンク
問合せ先
愛知県農業総合試験場
電話: メニュー【組織と業務】の各課室の番号におかけください
E-mail: 【本場】 nososi@pref.aichi.lg.jp
【東三河農業研究所】 nososi-toyohashi@pref.aichi.lg.jp
【山間農業研究所】 nososi-sankan@pref.aichi.lg.jp